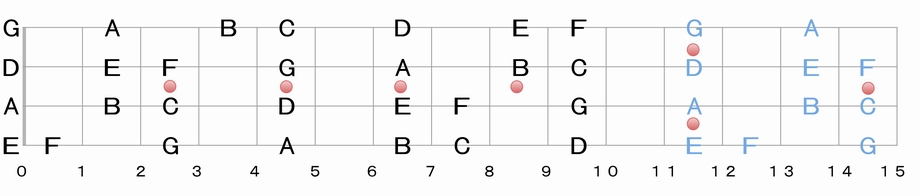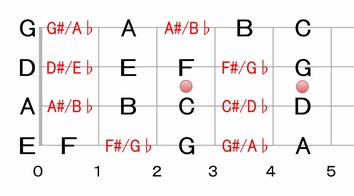2023/2/1 音楽理論 その① - 音名
 さて、今回からは音楽理論について書いていきます。
今回は、音名についてです。
さて、今回からは音楽理論について書いていきます。
今回は、音名についてです。
音名の呼び方は国によって違う
学校の音楽で習った「ドレミファソラシ」って、どこの国の音名の呼び方か知っていますか? 答えはイタリア語の呼び方です。 日本語での呼び方は「ハニホヘトイロハ」。
このように、音名の呼び方は国によって違います。 まずは下記の表を見てみてください。
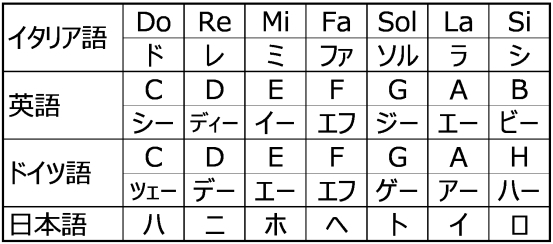
英語の音名とドイツ語の音名は、基本的に同じアルファベットですが、読み方が違います。 どちらもスタートはCで、そこから順番に並んでいますが、7番目の「シ」だけ英語ではB、ドイツ語ではHになります。
ロックやポップス、ジャズでは、基本的に英語の音名を使い、クラシックではドイツ語の音名を使います。 ロックやポップスのベースを弾きたいと思っている方は、英語の音名を覚えましょう。
名前のない音名たち
さて、英語の音名をベースの指板上で表すと、下記の図のようになります。
しかし、ちょっと待ってください。 例えば3弦の4フレット、CとDの間には音名がありませんね。 鍵盤楽器でいうと、黒鍵がこの音名のない部分なのですが、音名のないこの可哀想な音はなんと呼ぶのでしょうか?
空白のポジションには、シャープやフラットを付けると導き出すことができます。 3弦4フレットは、Cから見たらC#、Dから見たらD♭となります。 つまり、基準の音から半音高くなればシャープ(#)、低くなれば(♭)が付くことになります。
上記の図でわかるように、C#とD♭は同じ音です。 これを異名同音といいます。
こちらの動画も、是非ご覧ください。
次回は、「音楽理論」、倍音、について書いていきます。 是非楽しみにしていてください。

 トップページ
トップページ プロフィール
プロフィール レッスン
レッスン 無料体験レッスン
無料体験レッスン レッスン料金
レッスン料金 アクセスマップ
アクセスマップ お問い合わせ
お問い合わせ 動画
動画 レッスン講座
レッスン講座 News
News