2020/10/31 スケールとコードⅡ その④ - マイナーペンタトニックとメジャーペンタトニックの関係
 さて、前回はメジャーペンタトニックスケールの概要について、指板図やトレーニングフレーズを交えて書きました。
今回は、マイナーペンタトニックとメジャーペンタトニックの関係、について書いていきます。
さて、前回はメジャーペンタトニックスケールの概要について、指板図やトレーニングフレーズを交えて書きました。
今回は、マイナーペンタトニックとメジャーペンタトニックの関係、について書いていきます。
マイナーペンタトニックの指板図を少し広げてみる
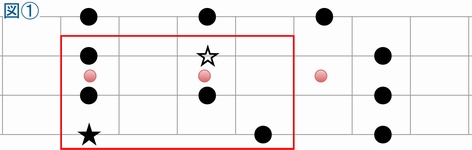 図①は、おなじみのマーナーペンタトニックの指板図に、もう少し上の音を足した指板図です。
足した上の音も、全てマイナーペンタトニックの音なので、ここまで伸ばした指板図の形を覚えておくと、フレーズの幅が広がりますね。
図①は、おなじみのマーナーペンタトニックの指板図に、もう少し上の音を足した指板図です。
足した上の音も、全てマイナーペンタトニックの音なので、ここまで伸ばした指板図の形を覚えておくと、フレーズの幅が広がりますね。
とはいえ、「基本的な形を覚えるだけでも苦労しているのに、これ以上覚えるのは無理!」と思っている方もいるのでは… いいえ、そんなに心配しなくても大丈夫です。
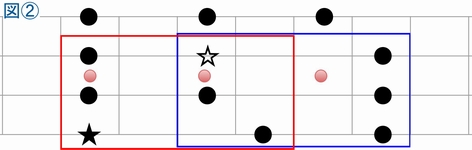 図②は、少し上の音を足した部分を、青枠で囲った指板図になります。
図②は、少し上の音を足した部分を、青枠で囲った指板図になります。
もう勘のいい方なら、ピンと来た方もいるのではないでしょうか。 そう、青枠で囲った部分は、メジャーペンタトニックと同じ形なのです。
マイナーペンタトニックとメジャーペンタトニックの基本的な形を覚えておいて、それを組み合わせることで指板の形が広がりました。 是非これをマスターして、フレーズの幅を広げてください。
マーナーペンタトニックとメジャーペンタトニックの形が曖昧な方は、下記を確認してみてください。
マイナーペンタトニックとメジャーペンタトニックは、実は同じ
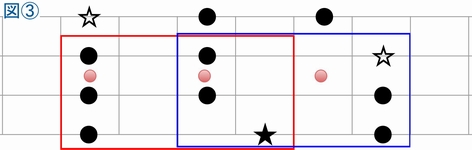 図③は、図②と同じ指板図ですが、ルートの位置がメジャーペンタトニックの位置になっています。
青枠で囲った部分が、おなじみのメジャーペンタトニックの指板図ですが、それにもう少し下の音を足した指板図が、図③になります。
図③は、図②と同じ指板図ですが、ルートの位置がメジャーペンタトニックの位置になっています。
青枠で囲った部分が、おなじみのメジャーペンタトニックの指板図ですが、それにもう少し下の音を足した指板図が、図③になります。
これは、同じ指板図なのにルートが変わるだけで、マイナーペンタトニックになったり、メジャーペンタトニックになる、ということなのです。
例えば図②のルートがAだとすると、図③のルートはCになります。 つまり、AのマイナーペンタトニックとCのメジャーペンタトニックは、ルートが変わるだけでスケール・指板図の形は同じ、ということになります。
さあ、ここまで理解したら、実際にこのスケールを使ってフレーズが弾けるようになればいいのです。 それには、サンプルフレーズに基づいてトレーニングするのが一番でしょう。
次回からは具体的にトレーニングの実践に入ります。
こちらの動画も、是非ご覧ください。
次回からは、「スケールとコードⅡ」、ペンタトニックの実践編を書いていきます。 是非楽しみにしていてください。

 トップページ
トップページ プロフィール
プロフィール レッスン
レッスン 無料体験レッスン
無料体験レッスン レッスン料金
レッスン料金 アクセスマップ
アクセスマップ お問い合わせ
お問い合わせ 動画
動画 レッスン講座
レッスン講座 News
News