2019/7/16 リズム感 その⑭ - 改めてリズム感を鍛えるⅠ
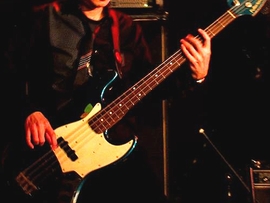 さて、前回はリズム練習が楽しくなる方法について書きました。
今回は改めてリズム感を鍛える、について書いていきます。
さて、前回はリズム練習が楽しくなる方法について書きました。
今回は改めてリズム感を鍛える、について書いていきます。
複雑なリズムになると、未だにリズムがわからなくなることがあります。 例えどんなに優れたテクニックを持っていても、リズムがわからなければ宝の持ち腐れですね。 もちろん、自信のあるテクニックがなければ、格好良く弾くこともできません。 だからこそ、リズムをしっかりと理解しておく必要があります。
今回は、リズムを理解するためのコツを3つのポイントにしてみました。
- 苦手なリズムを知る
- 譜割りを覚える
- 倍テンの感覚を養う
このポイントが掴めれば、リズムへの理解がスムーズになります。
苦手なリズムを知る
苦手なリズムを見つける方法は、意外にシンプルです。
-
譜面を読む場合
譜面を見ながら弾いていて、引っかかったり止まったりする場所が苦手なリズムです。 - 耳コピの場合
耳コピの場合は、聞いたリズムをすぐに再現できるかどうかがポイントです。 さらに、耳コピしたリズムを譜面に起こせるかどうかも、判断基準の一つとなります。
譜面を読む場合も耳コピの場合も、経験値が理解を左右します。 色々なリズムを聴くことで、すぐに理解できる判断力が身につきます。 なぜならリズムを理解する力は、それを経験した記憶力に関係するからです。
譜割りを覚える
楽譜の表記は、基本的に拍で区切られるように書かれています。 見やすさを保つために1拍単位や2拍単位で区切って書くことが多いです。 私も楽譜を書くときは、そのように心がけるようにしています。
譜割とは、それらのリズム表記を一つのまとまりにしたものと言えます。 従って、譜割りを覚えることが音符と休符の理解に繋がっていきます。
譜割りを理解できることは、頭の中でリズムの整理ができている証です。 音符の長さを音価と言いますが、音価の理解が、リズムを理解するためのコツとなります。
音価についてわからない方は、過去のレッスン講座を見てください。
楽譜は、表記上拍で区切られることが読みやすさの基本的なルールですが、演奏は必ずしもそうではありません。 ここで難しく感じるのがシンコペーションです。 拍や小節を越える音価が出てくると、急に難しく感じてしまうことがあります。
- 音価を意識すると、テンポがわからなくなる
- テンポを意識すると、音価がわからなくなる
- 音価もテンポもあいまいになる
このような状況を解決する方法として、倍テンの感覚を養う方法があります。 リズムが理解できない → 譜割が覚えられないときは、テンポを2倍や4倍にして、拍を細かく区切ってみてください。 その具体的な方法は、次回のレッスン講座に書くことにします。
こちらの動画も、是非ご覧ください。
次回は、「リズム感」、改めてリズム感を鍛える - 倍テンの感覚を養う、について書いていきます。 是非楽しみにしていてください。

 トップページ
トップページ プロフィール
プロフィール レッスン
レッスン 無料体験レッスン
無料体験レッスン レッスン料金
レッスン料金 アクセスマップ
アクセスマップ お問い合わせ
お問い合わせ 動画
動画 レッスン講座
レッスン講座 News
News