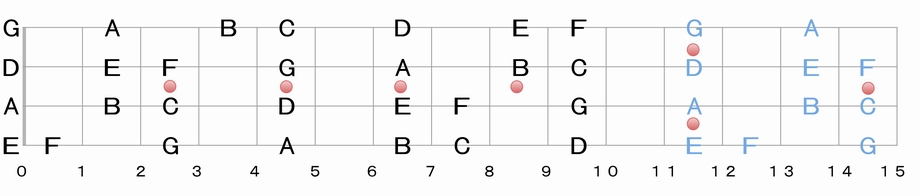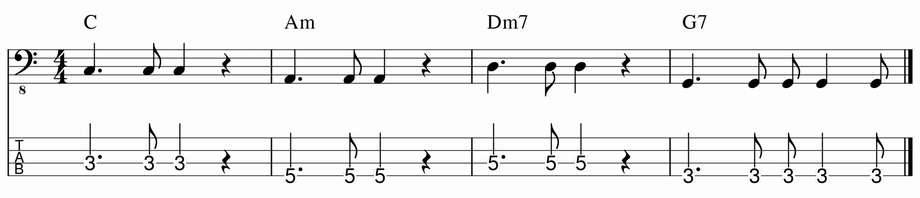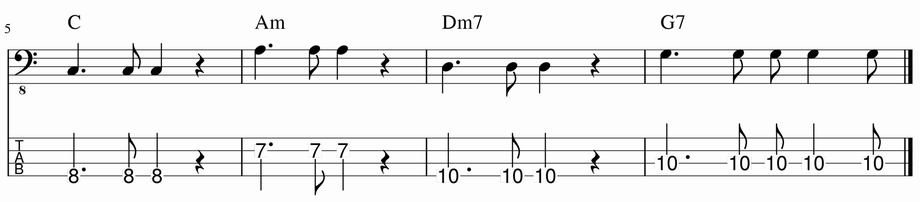2020/3/28 スケールとコード その③ - コードとルート音
 さて、前回は指板上のポジション、について書きました。
今回は、コードとルート音、について書いていきます。
さて、前回は指板上のポジション、について書きました。
今回は、コードとルート音、について書いていきます。
コードとリズムが書かれた譜面に、ベースが録音されていない音源を渡され、「これにルートだけでいいから、ベースラインをつけて」と言われたらどうしますか? コードに知識のない人だと、全く意味がわからないはずです。
コードには必ずルートがある
例えば下のような譜面です。
セッションなどで、よく渡される譜面です。 コードからルートを探すには、歌などのメロディは関係がないので、依頼する方もこうした譜面にすることが多いです。
さて、上の譜面には、C、A、D、G、という、見慣れた記号が書いてありますね? 感のいい方だとピンと来たと思いますが、ルート、というのはコードの一番最初に書かれる英語音名のことです。 ルートを確認するには、「m」や「7」は無視してもらって構いません。
コードのルートが分かったら、「スケールとコード その① - 指板上のポジション その①」 で学んだ指板の英語音名を思い出してみましょう。
指板の音名がルート
以前学んだように、指板には上のような英語音名が割り振られています。 この指板の音名こそが、ルートの正体となります。
先ほどのコードとリズムが書かれた譜面を、指板の音名と合わせてみましょう。 譜面にすると、例えば下記のようになります。
前後のフレーズによって、ハイフレットの方が運指がしやすい場合などは、下記のようなポジションを選択することも考えられます。
ルートは根音
コードは2つ以上の複数の音が、縦に積み重なっていると想像してください。 その一番下にある土台の音をルート(Root)と言い、日本式では根音(こんおん)といいます。
このように、指板の音名がコードのルートになります。 したがって、指板の音名を覚えておかないと、ルートを弾くことができません。 指板上のポジションを覚えることが、いかに大切かがわかると思います。
セッションやアドリブ演奏には、指板上のポジションを覚えるていることが欠かせません。 まだ指板上のポジションに自信のない方は、前回まで学んだ 「スケールとコード その① - 指板上のポジション その①」 を繰り返し確認して、覚えてしまいましょう。 それが上達への早道になります。
こちらの動画も、是非ご覧ください。
次回は、「スケールとコード」、3度と5度、について書いていきます。 是非楽しみにしていてください。

 トップページ
トップページ プロフィール
プロフィール レッスン
レッスン 無料体験レッスン
無料体験レッスン レッスン料金
レッスン料金 アクセスマップ
アクセスマップ お問い合わせ
お問い合わせ 動画
動画 レッスン講座
レッスン講座 News
News